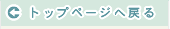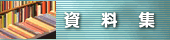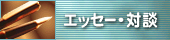精神科医の立場から
精神科診療所と医療観察法の今日的課題
大久保 圭策(精神科医)
2007.07
「心神喪失者等医療観察法(医療観察法)」が施行されてから既に2年が過ぎた。データが公表されている2007年4月までの間に、この法律の対象となった精神障害者は少なくとも654人。そのうち323人が入院となり、112人が通院処遇となっている。
日々の臨床の中で、医療観察法の存在を感じる機会は多くはない。むしろ、ほとんどないというのが実際ではなかろうか。学会のシンポジウムが何度か組まれ、時に商業誌も特集を載せた。司法精神医学の学会も出来た。しかし、開業精神科医のどれほどがこの法律に関心を持ち続けただろうか。
医療観察法から見えるもの
自分に直接関係のない事柄について関心を持ち続けることは困難だ。医療観察法関連問題委員会(注:大阪精神科診療所協会の内部委員会)では、大阪弁護士会からの依頼を受けて、医療観察法による鑑定の際に付添人(弁護士)に協力するという形で、医療観察法へのかかわりを続けている。
実際に関わってみないと見えてこないことはずいぶん多い。対象者の多くが受けてきた精神科医療の貧困、地域からの孤立、そしてしばしば不幸な生い立ち。”触法精神障害者”などというおどろおどろしいイメージを喚起する言葉には似つかわしくない、いかにも弱々しい生を多くの対象者は生きている。医療観察法における鑑定医が、あるいは付添人となった弁護士が、おそらくもっとも彼らのことを理解してくれる存在だったに違いないということも少なくないという現実がそこにはあった。医療観察法から見えてくることは、貧困な精神科医療と精神障害者が孤立せざるを得ない地域社会の現実である。
−医療観察法は実際に動いている−
法律は実際に動いており、少なくない民間の精神科病院は鑑定入院を受け入れ、あるいは指定通院医療機関になっている。そして、自治体立の精神科病院は、病床の一部を医療観察法のための病床にすることで入院処遇を受け入れ始め、入院医療・通院処遇に関する実際的な問題が議論され始めている。病院精神科医療の中では、確実に医療観察法は動き始めているのだ。そして、遠くない将来、現在の措置入院と同じ程度に日常的な業務になっていくだろう。
日常業務になってしまえば、賛成だ、反対だと言っていた時期の根本問題など、捨て置かれるに違いない。国会でも、学会でも、あれだけ“再犯予測が可能なのか”という問題が議論されたというのに、既に何例もおこなわれている医療観察法による鑑定(ふたたび同様の行為を繰り返すことなく社会復帰するために医療観察法による医療が必要か否かの鑑定)においても、再犯の可能性について緻密な議論を展開している鑑定書にお目にかかったことはない。
そうして、”疑わしきは、医療観察法に”という処遇が決められる。医療観察法は、司法の側からは、利益処分と考えられているから。
近未来の課題 〜医療観察法による医療から一般医療へ〜
通院処遇は、一応3年間が目安になっているから、あと1年すれば、通院処遇を終了した人たちが、一般の精神科医療に戻ってき始める。(通院処遇は、3年に満たずに終了することもありうるので、実際はさらに早い)医療観察法では、審判の結果「医療観察法による入院によらない医療」が必要と判断された場合、指定通院医療機関への通院が義務付けられる。保護観察所の精神保健観察を受けながらの指定通院医療機関への通院処遇が終了すれば、対象者は一般の精神科医療に戻ることになる。戻る際には、医療観察法による医療によらなくても、「ふたたび同様の行為を繰り返すことがない」というお墨付きが与えられる。そのお墨付きに意味があるとしても、意味がないとしても。
指定医療機関は限られているので、対象者がより近くの医療機関への通院を希望することは充分に考えられる。その中には、当然精神科診療所も含まれてくるだろう。この場合、自院への受け入れを拒否することは、医師法上はできないはずだ。そもそも、医療観察法の対象者であったことを理由に拒否するとなれば、甚だしい人権侵害ということになる。
医療観察法というような特別な法律、特別な医療を作るよりも、一般の精神科医療を底上げするべきではないかという反対論があった。否、そうではなく、特別な医療が必要なのだと国は医療観察法を作り、医療観察法病棟を建てた。それでは、その特別な医療とはどのようなものなのか。その中身は、ほとんど見えてこない。“医療観察法による医療”がブラックボックスになってしまえば、突然そこから出てきた人を、これからは”一般の医療でよろしい”と精神科診療所に預けられても、戸惑ってしまう。
医療観察法は、本当に良質な医療なのか?
“医療観察法による医療というような特別な医療は必要ない”ということ以上に、“特別な医療は逆効果なのじゃないか”ということをもっと考える必要があるように思う。
医療観察法の対象者になった過去は、おそらくそれだけで社会復帰阻害要因になる。どこの国でも、一度刑務所に入った人の再犯率は高い。再犯率の高さは、“刑務所帰り”というスティグマによるところがどの程度関係しているのかは考えてみる必要がある。新患が、医療観察法の処遇を受けていたと知って、そのことをまったく考えずに診療ができるだろうか。地域の福祉施設はどうだろうか。あるいは、アパートの大家は、就労先の関係者は。医療観察法の対象になるということは、社会的なマイナスを背負うということである。医療観察法による医療は、マイナスから出発せざるを得ない。
医療観察法の通院処遇に関するガイドラインには、クリティカル・パスというのが定められている。毎日が通院、デイケア、訪問看護で埋め尽くされ、それに保護観察所による精神保健観察が加わる。ガイドラインを見ているだけで窒息しそうな気分になる。
既に、通院処遇中の自殺者も出ている。ここを生き延びた患者は、どのような人になっているのだろう、と思う。濃厚な精神科医療は、短期間で患者を没主体的な存在にしてしまいはしないだろうか。
医療観察法は既に精神科診療所を巻き込んでいる
診療所精神科医療は、患者の主体性を尊重する。主体をねじ伏せるようなことは、もしそれが可能であったとしても、治療と呼べるかどうか。”医療観察法による医療”は、そこにわれわれの考える精神科医療を接木することが出来るようなものなのだろうか。その問いを、否応なくわれわれ自身が突きつけられる。
そして、医療観察法は、われわれ自身の問題となる。診療所精神科医療は新たな難問に直面することになるだろう。
※「大精診ニュース」(社)大阪精神科診療所協会発行 No.394(2007年2月号)
より一部改変の上転載