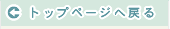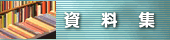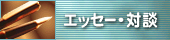審判・処遇についての適正手続上の問題点の概観
大杉光子(弁護士)
2004年3月27日
はじめに
心神喪失者等医療観察法(以下、「新法」という。)に反対してきた立場からはこの法律はすみやかに廃止されるべきだと考えるが、新法の施行によって現実に対象とされる人々が出てくる以上は、新法の問題点を整理しながら、それらの人々に対する人権侵害をできるだけくい止めるために何が必要なのかを考えてみたい。
これまで、精神科病院、刑務所等の刑事施設、ハンセン病療養所等、閉鎖的で社会から隔離された施設、社会的に声を上げにくくされている立場の人々が強制的に隔離収容された場所で、それらの人々に対する身体的精神的虐待、見せしめ的な制裁や様々な人権侵害が行われてきた。新法による指定入院医療機関も閉鎖的な隔離施設であり、ここでだけ人権侵害の可能性がないなどということはあり得ない。国がこの法律を作ったのだから、予想される人権侵害を防ぐための諸方策も、国が責任を持って作るべきである。
(なお、本稿は、基本的には2004年3月27日のシンポジウムでの発言をまとめたものであり、その後の最高裁規則等の内容や弁護士会等の準備状況を含んでいないことをあらかじめお断りしておきたい。)
1 新法で置き去りにされている問題
まずは、新法の審議過程で問題が指摘されながら、置き去りにされている問題について、主なものをあげてみる。
精神科医療・福祉の底上げについては、修正の際に、付則3条が加えられた。しかし、「精神医療、精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする」という努力義務規定に過ぎず、たとえば「精神病床の人員配置基準を見直し」と書かれてあるにもかかわらず、その後もいわゆる精神科特例には何ら手をつけられていない。それどころか、例年は認められてきたいわゆる社会復帰施設への施設整備費の補助金が、2003年度は要望通り認められないなど(注1)、実際には底上げどころか逆行している。いずれにせよ、精神科医療・福祉の底上げこそが必要である。
精神鑑定とくに起訴前簡易鑑定と検察官の起訴裁量についての問題点も、手をつけられていないままである。殺人事件でも心神喪失・心神耗弱で不起訴処分となったうちの約1割が簡易鑑定すらなされていなかったり(注2)、地検ごとに鑑定医1人あたりの件数に大きなばらつきがあったり(注3)等といった点については、ずさんな簡易鑑定と安易な起訴不起訴の問題として、審議過程でもかなり批判された。しかし、この法律ではその点には手をつけられていない。法40条1項2号(検察官が心神喪失者と認めて不起訴処分にした者について、裁判所が心神耗弱者と認めた場合には検察官に通知する制度)によって事後チェックがされるから適正化されるのではないかという見方もあるかもしれないが、この法律による鑑定は責任能力判断を求めるものとはなっていないため(37条2項参照)、チェック機能が働くかどうか疑問である。37条鑑定においても、対象行為を行った際の責任能力を判定する必要がある。
同時に問題なのは、刑事施設における医療がとても貧困なことである。常勤医がいるはずなのに週2、3回半日ずつしか医師がいない刑事施設もあり(注4)、診察を希望しても、なかなか受診できなかったり、准看護師から薬をもらうだけだったりといった例をよく聞く。必要な治療が受けられないだけではなく、精神症状を規則違反とされて懲罰を受けたり(注5)、保護房に放置されて亡くなっていたり(注6)、日常的に被収容者と接する刑務官に知識がないために医療につなげられていないと思われる例もある。弁護士会への人権侵犯救済申立事件でも、診察が遅れた、治療が受けられない、という被拘禁者からの申立は多い(注7)。刑事施設勤務医のなり手が少なく、加えて最近の過剰拘禁のために手が回らないのかもしれないが、24時間拘禁している施設において生命や健康に関わる責任は施設側にある(注8)。この問題は刑事施設の医療体制だけが問題なのではない。そもそも刑事訴訟法の原則通りに勾留が例外とされ、たとえ勾留されても保釈が原則であれば、拘置所は過剰拘禁にはならず、社会内において入院や通院によって治療を受ければいいはずである。そういう意味では、これは人質司法の問題でもある。
これらの問題点は、新法の有無にかかわらず、いずれにしても改善していかなければならない問題である。
2 新法に内在する問題点
新法そのものに内在する問題として主なものをあげる。
周知の通り、新法は、心神喪失・心神耗弱を理由として、不起訴処分や無罪判決を受けた人、有罪判決を受けたが減刑されて受刑しない人が対象である。実際に刑務所に入る人や他の事件で施設に収容される人は丁寧にはずされている(法33条2項参照)。実際に刑務所に入るかどうかによって治療の必要性は変わらないはずであるから、これは、刑事処分としては拘禁されない人をどうやって拘禁するのか、すなわち実質的には刑罰に代わる制裁という発想で作られているとしか考えられない。
また、正確に再犯を予測することは不可能であり、必ず誤って「再犯する」と判定され拘禁される人が生じることは明らかである。新法の処遇要件は、政府原案の「継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」から、修正によって「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って、同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要」に変わった。これについては、修正案の審議の中で、「再犯のおそれ」は削除されていないと繰り返し追及してきたが、政府答弁は、その点の批判を受けたから変えたのだ、医療必要性が中心的要件になったのだと繰り返した(注9)(注10)。その立法経過を見れば、「再犯のおそれ」があるから入院させる、退院させない、ということは許されない。
他方、精神障害者のみが特別に強制隔離されることは、「精神障害者は危険だからこういう制度が必要なのだ」という偏見をますます助長することになる。直接的にはこの法律の対象にならない人も、そういう偏見の目で見られることになりかねない。「らい予防法」が、ハンセン病の人々を療養所に強制隔離しただけではなく、社会にいる人も病気を隠さねば生きられない状況に追い込んだのと同じである。
法制度そのものに内在する問題は、法律を廃止しなければ解消することはできない。また、新法の対象にされる人をできる限り少なくするとともに、この法律と問題点を広く知らせること、差別偏見に対抗する啓発活動をすることが必要である。
3 手続き上の問題点〜原理的問題
憲法39条は、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と定めている。これは、遡及処罰の禁止、二重の危険の法理、二重処罰の禁止を定めたものである。新法は、不起訴の場合は別として、無罪判決を受けた人、有罪判決を受けて受刑しない人を対象としている。また、付則2条は、法施行前の対象行為について、法施行後に不起訴処分、無罪判決などがあれば、新法の適用を受けるとしている。これらは、前述の二重の危険の法理、二重処罰の禁止、遡及処罰の禁止などの憲法上の諸原則の趣旨に反する。
また、鑑定入院命令は、「鑑定その他医療的観察のため」とされているものの、「(入通院)決定があるまでの間在院させる」(34条1項)とあるように、実質的には入通院決定まで対象者を拘禁するためのものである。しかも、「対象者について対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き」(34条1項)という要件は検察官申立の要件(33条1項)と全く同じであるから、検察官申立がされれば当然に拘禁される仕組みになっている。
これが人身の自由を奪う制度であるがゆえに、法34条2項は、供述拒否権、付添人選任権、理由の告知と陳述の機会を与えているはずである。ところが、34条2項は、同時に、「心身の故障」がある場合にはこれらが必要ないとしている。これでは、憲法34条前段や31条の適正手続の保障の趣旨に反する。
いずれにせよ、この鑑定入院命令は、原則2ヶ月、延長してさらに1ヶ月の最大3ヶ月とされているが、事実関係を争う場合など、審判が3ヶ月で終わらない場合には、在宅での審判が必要になる。
他方で、この鑑定入院中の期間の治療については何ら規定がない。
なお、これらの適正手続違反という点については、この審判手続は刑事手続きではないから憲法に反しない、という反論はありえるが、刑事手続きでなければ適正手続きがなくても良いということにはならない。しかも、新法は、実質的には刑務所に行かない人に対する制裁の役割を果たしうるものであって、刑事事件に関連して強制されるのであるから、その不利益処分性からしても、少なくとも刑事手続きにおける適正手続きに準じた扱いがされるべきである。
4 手続き上の問題点〜刑事訴訟との比較
刑事訴訟であれば、秘密接見交通権(刑事訴訟法39条1項)、記録閲覧謄写権(同40条1項など)、伝聞法則(同320条1項)、自白法則(同319条1項)、補強法則(同319条2項)などの権利等が明文上認められているが、新法では「処遇事件の性質に反しない限り」刑事訴訟法の規定を準用するとされているだけで(24条4項)、明文規定がない。指定入院医療機関に入院させられてからの面会については92条2項に一応規定があるが、鑑定入院中については面会規定すらない。記録の閲覧については付添人に権利が一応認められているが(32条2項)、謄写については裁判所の許可が必要とされている(32条1項)。しかし、調書等の対象行為についての証拠書類だけではなく、鑑定書やカルテ等の医療情報についても、閲覧謄写が必要であり、制限されることがあってはならない。なお、現在の国選刑事事件において、記録謄写権は認められてはいるものの、その費用は支給されないことが多いが、これでは実質的には権利保障したことにならないことを付言しておく。
また、対象行為の存否についての審理の特則として、裁判官のみで構成される別の合議体での審理の規定があるが(41条)、この場合にも刑事訴訟法に沿った手続規定がない。この場合には、刑事裁判で言えば否認事件なのであるから、なおのこと刑事訴訟法に準じた手続が必要である。
5 手続き上の問題点に対して
きちんと審判で争うためには、先ほどあげた刑事訴訟法で保障されている権利が必要なだけではない。この審判段階だけではなく、その前段の捜査段階、公判段階の刑事手続き中の問題もある。たとえば、取調過程の可視化すなわち弁護人の立ち会い・テープ録音・ビデオ録画、検察官の手持ち証拠・医療情報の全面開示、セカンドオピニオン等が必要である。もちろん、取調過程の可視化や全面的証拠開示は、この法律の手続きだけではなく、そもそもすべての刑事事件において必要であるが、とりわけ、この審判の対象となる人々は防御能力が不十分な可能性が高いので、なおさら必要性が高い。捜査段階ではこの審判の対象になるかどうかわからない場合も多いであろうし、基本的にはすべての事件で取調過程の可視化や証拠開示がなされるべきである。
取調の弁護人立ち会いやテープ録音は、イギリス、アメリカ、イタリア、オーストラリア、台湾等でも行われており(注11)、日本も早急に導入すべきである。ただし、厳格にすべての過程を可視化しなければ、意味がない。暴行、脅迫を防ぐというだけではなく、誘導や微妙なやりとりの供述経過を明らかにすることは、自白調書の任意性、信用性を争う上で必要である。また、鑑定の過程もテープ録音されるべきである。どのようなやりとりからそのような判断をしたのかという判断過程の検証を可能とするためにも、誘導などによって供述がゆがめられていないことを確認するためにも、必要だからである。刑事裁判における鑑定よりも、この審判の鑑定は比重が大きいであろうから、その鑑定過程の適正を確保することはなおさら必要である。
また、この審判においては、伝聞法則がないので、警察・検察の証拠が本人・弁護人のチェックを経ることなくそのまま裁判所に提出されることになる。そうであれば、なおさら、本人に有利な証拠も含めた全面的証拠開示が必要である。
セカンドオピニオンについては、対象者・付添人が指定した医師が立会なしに面会して診察すること、その医師がカルテなどの医療情報にアクセスすること、それらの費用負担を国がすることを含む。
6 手続き上の問題点〜不服申立
不服申立制度としては、処遇決定に対する抗告(64条1項)、再抗告(70条1項)、鑑定入院命令に対する不服申立(72条1項)、鑑定入院命令の延長決定等に対する異議(73条1項)、退院許可等申立(50条)、処遇終了申立(55条)、処遇改善請求(95条)などが規定されている。
抗告は、「決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とする場合に限り」とされており(64条2項)、控訴理由と比べてもかなり限定されている。
また、鑑定入院命令に対する不服申立も、勾留に対する準抗告・抗告と比べてもかなり限定されている。これは、鑑定入院命令の要件が「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き」(34条1項)であるにもかかわらず、不服申立の際に「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要がないことを理由とすることができない」(72条2項)とあるように、まさにこの要件の欠如を争うことができないためである。これでは、不服申立ができるのは手続に違法がある場合くらいとも思われるが、それでは不服申立制度は絵に描いた餅になりかねない
また、最初の検察官申立審判の決定に対する抗告は必要的付添人制度とされている(67条)が、その他の退院許可申立等の審判や抗告では付添人は必要的とされていない。しかし、本人が申し立てする場合を考えてみてほしい。指定入院医療機関に拘禁されている本人が、一人で、どうやって、申立をするのだろうか。現状でも、日本では強制入院患者が10万人くらいいる中で、精神医療審査会への退院等請求は年間2000件弱、退院成功率は1%以下である(注12)。イギリスでは強制入院患者が2万人くらい、不服申立が年間約6000件、成功率は約20%だそうである(注13)。この差は、イギリスでは、公費で弁護士の援助を受けられるのみならず、アドボケート制度があり、カルテ開示請求権、セカンドオピニオンを得る権利などが保障されていることと無関係ではないだろう。それらが保障されていない新法の不服申立制度の実効性には疑問を持たざるを得ない。処遇改善請求にも同じ問題がある上、処遇改善請求の審査をする社会保障審議会は厚生労働大臣の諮問機関で全国で1つだけであり、機動性があるとは思えない。
なお、付添人が選任者である保護者の明示した意思に反して抗告できないという規定(64条2項但書)にも問題がある。付添人は、あくまでも、本人の権利擁護のための存在であって本人の利益のために行動すべきである。付添人としては、本人と保護者との意向が食い違う可能性がある場合には、できるだけ本人から選任してもらうようにすべきであろう。
7 不服申立制度の実効化のために
前述の不服申立制度を少しでも機能させようと思えば、かなりのフォローが必要である。
まずは、本人自身がどんな権利を持っているのか、どういう場合にどのような不服申立をすることができるのかを知らせることが必要である。一番の弁護人は、本人自身である。
次に、実際に本人が行動を起こすために必要な手段を準備しなければならない。たとえば、電話での相談や申立を可能とすることが考えられる。当然、病棟には本人がスタッフに気兼ねなく自由に使える電話があることが前提である。精神医療審査会への請求は、実際に受理されているのはほんの一部ではあるが、電話でも良いとされて実際に受け付けもされている(注14)。裁判所への申立であっても、たとえば民事調停の申立(民事調停規則3条参照)や家事審判・調停の申立(家事審判規則3条参照)は口頭での申立を認めている。また、簡単な申立書式を指定入院医療機関には必ず備え付けて、いつでも本人に無条件で渡して、スタッフを介することなく提出させることも必要である。そして、それらを受け付けるためには、専任の事務局体制と直通電話が必要である。これらのことを詳しく本人および家族や関係者に告知し、わかりやすいリーフレットやステッカーで広報しておくことが必要である。
そして、書面だけでは本人が主張を展開しきることは難しいと思われるので、申立を受け付けた後、少なくとも、審判の場合には審判期日を必ず開催したり、処遇改善請求の場合には現地での本人からの直接の意見聴取を義務づけたりして、本人の主張を整理しながら丁寧に聞き取ることが必要である。審判期日の開催は規定上は任意的とされており(31条1項)、処遇改善請求も「意見を聞かなければならない」(95条3項)とされているのみであるが、これでは本人の言い分が尽くせないおそれが強い。また、時間ばかりかかって結論が出ないのは困るので、審査期間には上限を設けるべきである。現行の精神医療審査会マニュアルでも1ヶ月以内に結論を出すことになっているが、実際には1ヶ月を超えていることが多い(注15)。ましてや、社会保障審議会は全国で1つしかないため、社会保障審議会の中に専門の部会を作って意見聴取などの対応をするようにしなければ、精神医療審査会以上に無駄に時間が費やされることになりかねない。
このように、不服申立を本人自身が行えるための制度保障は必要であるが、その上でさらに、できるだけ弁護士の援助を得て行えるようにすべきである。そのために、審判については付添人、改善請求については代理人を、国の費用でつけることを保障すべきである。また、前述のセカンドオピニオンやカルテ開示などの諸権利の保障は当然必要である。
8 手続き上の問題点〜その他の権利保障
新法の制度には、再審制度がない。しかし、裁判が誤ることがあることは、再審によって死刑台から生還した人々の存在が雄弁に物語っている。しかも、新法では、前述の通り、刑事訴訟法並みの手続規定すらないのである。そうであれば、なおのこと、誤判を事後的に正す制度が必要不可欠である。また、事後的に入通院決定の誤りが明らかになった場合には、刑事補償に準じた補償が必要である。この点、新法の入通院処遇は医療を与えるのであるから本人にとって利益であり補償の必要はないと考えられているようであるが、自己決定に基づかない強制医療は不利益処分の性質を持つ。しかも自由の制約を伴うのであるから、誤って強制入通院を科した場合に補償が必要なことは明らかである。刑事訴訟のみならず、この審判制度が似ているという少年審判にもこれらの権利がある。新法にこれらの規定がないのは、法の欠陥である。
また、必要的付添人制度は、最初の検察官申立の入通院審判とその抗告審のみに限定されているが、これでは、実際に審判制度を機能させることは困難である。
なお、付添人が出席していれば本人不在でも良いとされているが(31条8項参照)、本人に告知聴聞の機会がないままの状態で審判を進めること自体が問題である。
9 処遇上の問題点
入院期間についての上限がないということは、いつまでも退院できないという可能性がある。厚生労働省のガイドラインでは入院期間は18ヶ月とされているようだが、退院を決めるのは裁判所である。指定入院医療機関が退院許可申立をしたときに裁判所がどのような判断をするのかが問題である。
そもそも、新法の医療や処遇の章には、本人の権利保障規定がない。指定医療機関や保護観察所などの権能については規定があるが、肝心の本人がどんな医療を受ける権利があるのかについてさえ、本人の立場から見た規定がない。本人を無視してどんな「手厚い医療」があるのか疑問である。
指定医療機関などの権能の濫用を防ぐための方策についても、ほとんど規定がない。厚生労働大臣が、厚生労働省の職員に報告を求めさせたり立ち入り調査や質問をさせたり出来るという規定はあるが(97条「必要があると認めるとき」)、定期的な報告・審査すら規定されていない。
また、地域での生活に向けた国の支援については、付則に宣言的な規定はあるが(付則3条3項)、具体的には、保護観察所を中心とした関係機関の連携ということでしかなく、これでは監視の目を張り巡らせるだけではないかと思われても仕方ない。本当に「社会復帰」(この言葉自体、どういう社会に復帰するのかという疑問はある)が目的だというのであれば、今の社会的入院とされる人々がなぜ退院できないのかという分析の上に、当事者の声を反映して、たとえばアパートを借りるための公的保証人制度や年金や生活保護などの経済的保障、本人が安心できる場の保障などの具体的な施策を、国の責任で予算の裏付けを持って実施することが先である。
10 処遇上の問題点に対して
まずは、本人自身がどんな権利を持っているのかを知ることが大切である。そのために、口頭での権利告知だけではなく、日常的に確認できるようなわかりやすいパンフレット、権利ノートが必要である。
そして、治療においては、治療計画策定への参加も含めて、インフォームドコンセントによって本人の理解と納得の上に進めるべきである。医者−患者関係というのは権力的関係であり、他科でも気になっていることを納得できるまで全部聞いて自分の思いを伝えることは困難であるが、この指定入院医療機関が強度の拘禁施設であることを考えればなおさら困難であろう。それゆえ、本人の立場で一緒に説明を聞き、気になる点、納得がいかない点を医療側に問い返して説明を受けるための、本人自身が選んだ権利擁護者、アドボケートが必要である。このアドボケートは、医療機関から独立していることが絶対に必要である。イギリスのブロードモア高度保安病院でもアドボケート制度を取り入れているそうである(注16)。
カルテなどの医療情報に対して、本人やその代理人がアクセスできることは、不服申立の際には特に重要であるが、日常的に指定医療機関を監視し、適切な医療を提供させるためにも必要である。セカンドオピニオンも同様である。
他方で、個人情報の流用・拡散は厳重に禁止されるべきである。新法の対象であったということは何重ものスティグマとなって、この法律による処遇の終了後も本人の社会生活を困難にしかねない。「関係機関の連携」の名の下に、不必要に個人情報が流出しないための管理が必要である。
また、閉鎖的な環境における人権侵害を予防するためにも、本人が社会との接点を失わずに早期退院につなげるという意味でも、入院中の外部との交流の確保は重要である。手紙、電話、面会などを自由に行えること、外部からの情報、たとえば、新聞、書籍、テレビ、インターネットなどを自由に選択して情報を得ることも重要である。
なお、本当は、これらのことは、新法の指定医療機関だけではなく、それ以外の精神科病院でも問題になることである。しかし、新法の指定医療機関はとりわけ拘禁性が強いことから、なおさら人権侵害のおそれが高く、それゆえに、なおさら権利保障が必要だということになる。このような制度を作って運営する国が、これらの権利を保障する責任を負うべきである。
11 指定医療機関に対して
閉鎖的な施設では、往々にして、人権侵害が起きる。それは、たまたまその施設のスタッフが悪かったということで片づけられることではなく、歴史的に様々な病院、刑務所、施設等で繰り返されてきたことを見てもわかるように、強制力を行使して拘禁することを繰り返すことで人権に対する感受性が麻痺し、たやすく人権侵害が起きるのだろうと思われる。
だからこそ、運営する側の善意にゆだねることはできず、それを防ぐための制度が必要である。厚生労働省が管轄する施設を厚生労働省が監督するだけでは不十分であり、第三者機関による調査、監督、抜き打ち検査などが必要である。これは、定期的に入院継続の審判が行われるから良いということにはならない。拷問等防止ヨーロッパ委員会(CPT)の活動が参考になろう(注17)。
また、プライバシーに配慮しつつも、指定医療機関のスタッフの配置や予算配分、対象行為別・診断名別の入院者数、入院期間、行動制限の種別・回数・理由、外出・外泊実施頻度、退院許可等申立・処遇改善請求回数・結果、入院継続審判結果などのデータの月次・年次報告等の情報公開が必要である。
12 外部の人間の課題
基本的には、国が作った制度であるから、国が人権侵害を防ぐ責任を持つべきであり、そのための方策を国自身が整備すべきである。
しかし、自浄作用には限界があり、たとえこれまで述べたような制度を作ったとしても、国に任せておいて安心することはできない。外からの働きかけがなければ、仮に制度があっても実効性を持たないであろう。一番怖いのは、自分には関係ないという無関心である。閉鎖された空間にいる、ただでさえ声を上げにくい人々のことを社会が忘れてしまったらどうなるのかという実例は数多くある。そのことを私たちは忘れてはならないだろう。
ひとつは、不服申立を受けとめるシステムを作ることである。弁護士の端くれとしては、福岡や大阪、名古屋、広島、岡山、京都などの弁護士会ような精神保健当番弁護制度を全国的に広げることが必要だと考えている。これは、精神科病院に入院中の人から弁護士会に電話があると、たとえば原則として4日以内に弁護士が直接本人に電話をして事情を聞いた上、10日以内に病院に行って直接本人に会って話を聞き、依頼により代理人として退院請求や処遇改善請求を行うという制度であり、弁護士費用を払えない人のための法律扶助制度も合わせて作っている。これと同じような制度を、少なくとも指定入院医療機関のある地域には作らなければならないだろう。その際には、精神科医やPSWなど、様々な人たちの協力もお願いする必要があるだろう。
また、入院中の人と、文通したり面会したり、大阪での精神医療オンブズマン制度のような病院訪問活動などをしていくこと、その中で、入院している人から要望を聞き取ったり、その意向を医療機関側に伝えたり、といったアドボケート活動もできていけばと考える。これは、弁護士等の資格に関わりなくできることである。
そして、情報公開をさせることも必要である。もちろん、指定医療機関側が積極的に行うべきことではあるが、自主的にしないのであれば、情報公開法などを活用して外からさせていくことも必要である。
おわりに
以上、心神喪失者等医療観察法の問題点と人権侵害をできるだけ防ぐための課題を考えてきた。これらの課題がすべて実現されたところで、人権侵害がなくなるわけではない。今後、最高裁規則や厚生労働省令、運用細則などによって新法が具体化されていくことになるだろうが、それらの制定過程に対する働きかけとともに、実際の運用に対する監視や働きかけを様々な立場の人々と協力して行っていきたい。
「2004年3月27日 法と精神医療学会シンポジウムより」
出典:『心神喪失者等医療観察法の問題点の整理〜人権侵害を防ぐために何が必要か〜』改題「法と精神医療」第19号(2005年)
注釈 一覧
(注1) 毎日新聞2003年6月8日 本文に戻る
(注2) 森山公夫ら「平成13年度厚生科学研究費補助金(障害保健福祉総合研究事業)措置入院制度のあり方に関する研究 『触法精神障害者』の精神医学的評価に関する研究」 本文に戻る
(注3) 毎日新聞2002年2月25日朝刊 本文に戻る
(注4) 読売新聞2003年9月5日朝刊等 本文に戻る
(注5) 大阪高等裁判所2000年6月15日判決(懲罰処分取消等請求事件)等 本文に戻る
(注6) 法務省死亡帳調査班による調査結果報告(2001年6月13日)等 本文に戻る
(注7) 日弁連拘禁二法案対策本部発行「刑事施設等における人権救済事例集」等 本文に戻る
(注8) 「一般に、被疑者らを拘禁する拘置所においては、被拘禁者の身柄を適切に管理する責務を有しているが、かかる被拘禁者に対する医療については、拘禁の性質上被拘禁者の行動の自由を制限し、疾病にかかった被拘禁者が自由に外部の医師の診療を受けるのを制限することができる反面として、拘置所長、看守ら拘置所職員は、その責務において被拘禁者の生命、身体の安全のため、その病状に応じた適切な措置を講ずべきことは当然のことといわなければならない。」(大阪地方裁判所1983年5月20日・判例時報1087号108頁)等 本文に戻る
(注9) 「この衆議院における修正は、まず第一に、本制度による処遇の対象となる者は、対象行為を行った際の精神障害を改善するために、この法律により医療が必要と認められる者に限られることであり、そして、二番目に、このような医療の必要性が認められる中で、すべてではなくて、精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だけが対象となることを明確にするということによりまして、本制度の処遇の要件というものを制度の目的に即した、今申し上げた社会復帰を促進するという目的に即した限定的なものにしようということでございまして、様々な批判を踏まえてこのような修正を行ったわけであります。」(2003年5月29日参議院法務委員会・提案者塩崎恭久衆議院議員) 本文に戻る
(注10) 「衆議院におきまして修正された要件につきましては、これまで修正案を御提案なさった委員がお答えなさっていらっしゃるとおり、政府案に対する様々な御批判や御懸念等を踏まえまして、これを解消するためにその要件を明確化するとともに、対象者の社会復帰を促進するという本制度の目的に即した限定的なものとされたものだと理解しております。」「すなわち、本制度による処遇の対象となる者は、対象行為を行った際の精神障害を改善するためにこの法律による医療が必要と認められる者に限られること、このような医療の必要性が認められる者の中でも精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だけが対象となることを明確にされたと、これらによりまして、この制度による処遇の要件を制度の目的に即した限定的なものにしたというふうに理解しております。」(2003年6月2日参議院法務委員会、厚生労働委員会連合審査会・森山真弓法務大臣
「この修正案によりまして医療の必要性が中心的な要件になったというふうに私は理解をいたしております。」(同審査会・坂口力厚生労働大臣) 本文に戻る
(注11) 日本弁護士連合会「取調べの可視化(録画・録音)で変えよう、刑事司法!」等 本文に戻る
(注12) 2000年度の退院および処遇改善請求件数1861件、審査件数1347件。審査結果は、退院命令15件、入院形式変更命令60件、改善命令2件。(山崎敏雄ら平成13年度厚生科学研究費補助金入院中の精神障害者の人権確保に関する研究分担研究報告書『人権擁護のための精神医療審査会の活性化に関する研究』) 本文に戻る
(注13) サイモン・フォスター(MIND主任弁護士)講演「精神障害者に対する救援活動〜イギリスMINDの経験に学ぶ」(2004年3月10日京都弁護士会) 本文に戻る
(注14) 2000年度の退院及び処遇改善請求の電話相談件数8349件、そのうち受理件数179件。(前出山崎敏雄ら「人権擁護のための精神医療審査会の活性化に関する研究」) 本文に戻る
(注15) 2000年度の退院及び処遇改善請求の請求受理から審査結果の通知まで平均41.4日。1ヶ月以内に通知されている審査会は59カ所中20カ所にとどまる。(前出山崎敏雄ら「人権擁護のための精神医療審査会の活性化に関する研究」) 本文に戻る
(注16) 前出サイモン・フォスター講演「精神障害者に対する救援活動〜イギリスMINDの経験に学ぶ」 本文に戻る
(注17) ティモシー・ハーディング(ジュネーブ大学附属法医学研究所所長、CPT専門家委員)「触法心神喪失者:再犯予測にもとづく処遇は可能か?」(2002年9月5日(社)自由人権協会における講演録) 本文に戻る