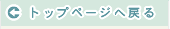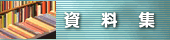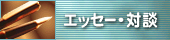「医療観察法」による地域処遇は制度破綻を免れない
岡崎伸郎(仙台市精神保健福祉総合センター)
2006年5月
要旨
心神喪失者等医療観察法に関する議論は、審判や入院医療の段階に集中しがちだが、実はそれ以上に多くの深刻な問題を抱えるのが、退院後の通院医療を含めた地域処遇である。
指定通院医療機関の配置は、量、質、地域バランスのいずれも、対象者の社会復帰促進というスローガンの実現から程遠い。また指定通院医療機関、保護観察所、地方自治体の権限や役割分担も、通院中断時の対応など肝心な点で未整理なままである。特に本法で定める精神保健観察には強制処遇的な側面があるにもかかわらず、その実施主体である保護観察所に何の権限も付与されていないのは致命的である。一方で本法には地方自治体の義務規定はなく、精神保健福祉法等に基づいた対象者の支援という従来からのスタンスに留まる。こうした構造的欠陥のため、「地域社会における処遇のガイドライン」や、それをもとに都道府県ごとに策定した「運営要領」の随所に破綻を生じさせる結果となっている。例えば「処遇実施計画」の中で、通院・服薬の遵守や保護観察所との定期的連絡といった強制処遇の部分と、デイケアや社会資源の活用など自己選択による部分とを明確化せずに運用すれば、重大な誤解やトラブルを引き起こす危惧がある。また本法による再入院要件(再び同様の対象行為を行う恐れ)と精神保健福祉法の措置入院要件(いわゆる自傷・他害の恐れ)との関係を曖昧なままにしたことは、本法で対応できないことを精神保健福祉法に転嫁したとの謗りを免れず、現場での判断が混乱するのは必定である。
そもそも鍵や塀のない茫洋とした“地域”をフィールドとした強制処遇制度にはリアリティが乏しく、破綻を免れないと言えよう。国は近い将来、指定入院医療機関の不足を補うための姑息的法改正を検討せざるを得なくなると予想されるが、それを機に法の施行を当面凍結して抜本的に再検討すべきである。
I .はじめに
多くの精神医療・保健・福祉関係者、団体が反対や危惧を表明する中で成立した「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律」(以下、医療観察法ないし本法と略)は、附則により公布から2年以内に施行することとして準備が行われ、期限ぎりぎりの2005年7月15日に施行された。本稿の元になる学会シンポジウムは施行の約2ヶ月前に行われ、執筆はまさにこの施行期日を挟んだ微妙な時期になされているのだが、筆者の見るところこの間の準備状況は、本法の円滑な運用を期待させるものからは程遠く、むしろ至るところでの制度破綻を予見させるものである。
医療観察法に基づく制度を大きく分けると、(1)審判の段階(鑑定入院の問題を含む)、(2)指定入院医療の段階、(3)指定通院医療を含む地域処遇の段階、の三つになる。
大方の精神科医の関心は、ともすると(1)、(2)に集中しがちである。実際(1)、(2)のなかには、法案審議段階で批判の集中した“再犯予測”可能性の問題と、それに代わって示された“リスクアセスメント”概念の有効性をめぐる問題、鑑定入院先の確保の問題、鑑定期間中の治療および行動制限の範囲と法的根拠、鑑定期間中の責任の所在、指定入院医療機関の絶対的不足とこれを補うための“代用病棟”案の是非、など争点が多く、これらを姑息的にクリアするために、施行直後の一部法改正が取り沙汰されるような状況である。
しかし実は(1)、(2)と比べても、より深刻な課題を抱えるのが(3)である。本稿では特にこの部分に焦点を当てて問題点をまとめ、広く精神医療・保健・福祉関係者の議論に供したい。
II.指定通院医療機関の役割と限界
まず、指定通院医療機関の確保状況について見る。国の説明によると、対象者の地域社会への復帰が円滑になされるためには、対象者が無理なく通院できる距離に指定医療機関が配置されることが必要であることから「設置主体に関わらず、各都道府県に最低2ヶ所、人口100万人当たり2〜3ヶ所程度を指定する」としている。
法施行直後の2005年8月5日時点での指定数は、上記に照らした設置目標数が382であるのに対して216(旧国立8、自治体立38、民間170)に留まっており、埼玉県と京都府が空白地区、5県が1医療機関のみとなっている。しかも指定のプロセスたるや、厚労省の意向にしたがって動かざるを得ない都道府県が、説明もそこそこに病院の了承を取り付けてリストアップしたものがほぼそのまま確定した、というのが本当のところである。したがって病院側の本法についての理解度もまちまちであり、現実に提供できる医療にも相当の格差があると言わざるを得ない。
「通院処遇ガイドライン」で国の示した医療内容は、デイケアや訪問看護の利用を当然のメニューとするなど、包括的でかなりレベルの高いものである。したがってそれが本当に実現されるならば、一般精神医療のモデルシステムとしても寄与し得るものであろう。
一方、本法の強制処遇的な性質を考えた場合、ガイドラインに明示したからには、それは努力目標といったものではあり得ず、地域格差などを許さないminimum requirement でなければならない道理である。しかるに現実には、複数施設の併用を認めた上でもなお、圏域としてガイドラインの水準をクリアできるところの方が稀であるから、まさに画に描いた餅である。
民間病院サイドには、指定への協力のためには自治体立病院や(旧)国立病院が率先して役割を担うことが当然の前提であるという論調が強く、公・民が牽制し合う構図となっている。指定通院医療に見合う財政措置が十分なされるのかも不透明である。
現場で最も問題になると思われるのは、通院医療計画を実施する場合の責任と権限の所在が極めて不明確なことである。地域処遇制度が動き出せば、対象者の病状の急変はもとより、そうとは限らない通院中断や連絡の途絶など、さまざまの程度のコースアウトが予想される。それが精神科臨床の日常というものであり、そうしたことを完全に回避することなど不可能である。一般臨床であれば、暫く様子を見て患者や家族からの連絡を待つ、という対応で何ら咎め立てされるところはない。しかし一定の管理下に置かれる本法対象者となるとそれでは済まない。問題はこのような場合に、主治医を含む指定通院医療機関の職員が、訪問(往診)、受診勧奨、受診援助、身柄の確保、病院への(場合によっては強制的な)搬送等の業務をどこまで担うのかについて、指定医療機関、保護観察所、地方自治体の間でコンセンサスが得られていないことである。国に言わせれば、医療に関することは医療機関の責任で、ということになるが、コースアウトしたケースをコースに引き戻すための対応がすべて医療の守備範囲なのか、保護観察所の行う精神保健観察の範囲なのか、両者の共同責任なのか。この点については、都道府県によっても申し合わせが錯綜している。錯綜した結果、指定医療機関も保護観察所もマンパワー不足を理由に主導的に介入することを手控え、対象者の状況がよくわからないまま時が流れるという危惧がある。
ちなみに国の発した「通院処遇ガイドライン」では、「クリティカルパスから外れた経過を辿る通院対象者に関する取扱い」の項目で「その場合の取扱いについては関係機関と相談の上で柔軟に対処するものとする。」と素っ気なく述べているだけである。ガイドラインの名に値しない記載と言わざるを得ない。
III.保護観察所の役割と限界
本法が取り沙汰されるまでは精神医療関係者の間であまり知られることもなかった保護観察所は、法務省の地方出先機関であり、本来は矯正〜更生施策を管轄する役所である。したがって精神障害者への対応という点では、ゼロからのスタートに等しい。そういう事情はあるにしても、本法における保護観察所の役割(第19条)は極めて重大であり、対象者の生活環境の調査、調整、精神保健観察(第106〜107条)の実施、関係機関相互間の連携確保など広汎な任務が規定されている。これを見れば、保護観察所が地域処遇の実施主体であることは紛れもない。
実際にこれらを担う専門職ということで、保護観察所のなかに社会復帰調整官というポストが新設された。原則として精神保健福祉士からの任用である。ところがその配置数は、目下のところ保護観察所ごとに1名に留まっている。本法対象者が全国で年間約300人とすると、運用開始後数年も経てば、各保護観察所とも常時数十人の対象者を抱えることになる。そのいずれもが複雑困難ケースであることを考えると、わずか1名の社会復帰調整官でどれほどのことができるのか懸念する声が上がるのも当然である。
退院予定地の社会復帰調整官は、入院中から対象者との面接等を重ねて、退院後の生活設計全般の調整を行うとされているが、なかでも勝負どころの住居確保は困難を極めると思われる。社会復帰調整官という特殊な肩書きの公務員が、例えば民間アパートの大家との交渉に臨んで本法制度を説明することで、対象者への差別偏見が霧消する、というほど構図は単純でない。むしろ地域住民の警戒感を助長して歩く結果になることも予想される。そうした苦戦の末になにが起きるか。ただでさえ地域に数少ない生活訓練施設等に、なし崩し的に対象者の受け入れが偏っていくという事態がありうる。
さて、国は本法の目的が対象者の社会復帰支援にあると強調しており、そのコンセプト自体は否定されるものではない。ただしこれは法案審議段階で、重大触法行為の再発予測が不可能であるにもかかわらずそれができることを前提とした再犯防止制度には科学的根拠がないと論難されたことをふまえた、いわば隠れ蓑である。しかしいくらソフト路線を装っても、地域処遇の根幹が、再犯につながるような病状悪化を防ぐための生活の“監視”(国は“見守り”と婉曲に表現している)であることは隠れもない。それが保護観察所の行う精神保健観察というものであり、地方自治体職員が日常行っている地域精神保健福祉活動のスタンス(同意を前提としたサービス提供)とは別のものである。
問題は、このような強制的性質を内包する精神保健観察であってみれば、それを貫徹するためには何らかの権限がなければならないはずなのに、それが与えられていないことである。例えば当初の計画に反して通院中断した場合、社会復帰調整官が頻繁に連絡を試みて受診勧奨することはあっても、保護観察所長名で受診命令書を発し、それにも従わない場合はこのような手段で受診させる、といった権限を伴うプロセスの規定がない。それでどういうことになるかというと、主治医の診察がなければ治療できないだけでなく医学的アセスメントができないわけだから、精神保健観察期間を延長するのか終了するのかという基本的判断すらできなくなる。一般医療なら容認される“フェードアウト”が本法対象者では許されないはずなのに、それを許さないようなシステムになっていないということである。
このような弱点を露呈しているのが、施行前からとかく批判のあった「地域社会における処遇のガイドライン」である。この中では、保護観察所の連絡調整機能ばかりが強調されており、有事の際に原則として社会復帰調整官が臨場して対応する、という地域保健従事者から見れば当たり前ともいえる一語すら見られない。そうしたことが地方の不信を招く結果となっている。
IV.地方自治体の役割と限界
本法の条文に都道府県・市町村の責務や努力規定が全くないということは、致命的な欠陥である。一言半句でもそれがあることで、地方自治体にとっては予算措置を講じてでもことに当たる根拠が生じるのであって、それがなければ金も人もつけられないのは、他のさまざまの法制度と同様である。それにも関わらず、保護観察所(つまり国)の力でできないことを地方に転嫁しようとする姿勢が至るところに見え隠れするために、地方の反発は強い。
地方における準備作業では、国の定めた「地域社会における処遇のガイドライン」をもとに、都道府県ごとの「運営要領」を策定することとされていた。そのプロセスで、上記の問題をめぐる保護観察所と地方とのせめぎ合いが各地で噴出したのである。象徴的なのは「運営要領」の策定主体についての規定である。保護観察所としては「保護観察所と県が共同で策定する」という文言にもっていきたいのだが、地方の言い分では共同策定は法理上あり得ないのであって、「保護観察所が県の協力のもとに策定する」という表現がぎりぎりの線だということになる。結局は、本省からの指示もあって譲らない保護観察所が押し切ったところが多いようであるが、両者の認識に根本的な食い違いを残しての施行は、今後の運用に影を落とすと見られる。
誤解のないように付け加えるが、地方自治体サイドが本法制度の運用にハナから非協力ということではない。対象者は精神障害者なのだから、精神保健福祉法その他に基づいてできるだけの支援をするのが当然であり、それ以上でも以下でもないというスタンスである。
そうはいっても実際には協力したくてもできない場面が出てくる。例えば広大な北海道・東北ブロックには、施行時現在、指定入院医療機関が岩手県内の1ヶ所しかない。こうなると遠隔県の職員が、対象者の入院中から病院訪問してケースワークを行うだけの予算はないから、退院までのことは社会復帰調整官頼みということになる。また入院中の外泊時の安全確保は、指定入院医療機関が責任を持つことになっているが、ここでもマンパワーの問題が重くのしかかる。こうしたさまざまの限界の中で、対象者の地域社会への円滑な移行が可能なのか、訝る向きが多い。
V.処遇実施計画の曖昧な構造
「地域社会における処遇のガイドライン」の根幹は、保護観察所がケア会議等で協議の上決定したり見直したりする処遇実施計画である。そのなかの医療に関する部分が、「通院処遇ガイドライン」に基づく個別の治療計画と重なり合う関係になっている。
処遇実施計画の策定に当たっては、「(保護観察所が適当でないと認める場合を除き)対象者がケア会議に出席して意見を述べることができる」とされ、さらに「計画内容について対象者に懇切・丁寧に説明し、対象者の同意を得るよう努める」という文言が頻出する。
こうした基本姿勢は、そうでないよりは確かに望ましいことであろう。しかし、あたかも障害者ケアマネジメント導入における本人参加やインフォームドコンセントの原則を引き写したかのような綺麗ごとだけでは済まないのが本法制度であるはずだ。
つまり処遇実施計画のなかには、通院・服薬の遵守、保護観察所との定期的連絡といった、本人同意の有無に関わらず従ってもらわなければならない強制処遇の部分と、デイケア利用、社会資源活用といった、自己選択・本人同意の下に行う部分とが混在しているのである。そのような二本立ての構造になっていることを明確にしない処遇実施計画は、運用上さまざまの誤解やトラブルを引き起こすと思われる。対象者にとって、場合によっては詐欺的ですらあろう。
もちろん、強制処遇部分を明確にしたところで、先にも述べたようにそれを実行するための権限がはっきりしない以上、空文に帰することになる。そうした事情がある限り、この点が曖昧になるのは必然的帰結と言えよう。
VI.精神保健福祉法との関係の不明確さ
さまざまの問題をはらむ地域処遇制度の中でも、最も危惧する声の大きいのが、病状悪化時などの緊急対応指針の不明確さである。各ガイドラインの中では、入院を要するような場合の選択肢として、(1)医療観察法による指定入院医療機関への再入院、(2)精神保健福祉法による入院(任意入院、医療保護入院、措置入院のすべてを含む)、のいずれも可能であるとされている。ところが(1)は、保護観察所から地方裁判所への再入院申し立てに始まって、改めて鑑定を行った上での審判、再入院決定、という遠回りなプロセスを踏まざるを得ず、緊急の役には立たない。そこでまず(2)で対応しておいて、その治療過程の中で必要が認められれば(1)の申し立てを検討することになる、と国は説明している。
このようなフローは一見現実的に見えるが、実は医療観察法の再入院要件(再び同様の対象行為を行う恐れ)と精神保健福祉法の措置入院要件(いわゆる自傷他害の恐れ)との関係を曖昧にしたまま、医療観察法でできない部分を精神保健福祉法に転嫁したに過ぎないのである。任意入院で対応できるようなケースならそれでもよかろうが、危険な病状の場合は、本法による再入院と措置入院との適用基準の如何が問題になる。例えば放火によって本法の対象となった人が、精神保健観察中の病状悪化によって再び放火未遂で警察に保護されたとする。この場合、たとえ精神保健福祉法24条による警察官通報が先になされたとしても、保護観察所は少なくともそれを知ったと同時に、本法による再入院検討の手続きに入るべきケースであろう。しかるに、まずは措置入院等でやってみて、という前提を許してしまうのでは、法の不適正運用との謗りを免れない。
筆者は以前、全国規模の公的会議の席で法務省担当者に、医療観察法の再入院要件と措置入院の要件との関係について問うたことがあった。そのときの法務省の見解では、両者は包含関係ではなく、双方独立の判断体系であるとの見解であった。だとすれば、緊急事態に臨んで現場担当者が依るべき一元的な基準はないということになる。
国が本法による再入院の門戸を狭くしたがる裏には、ただでさえ足りない指定入院病床が再入院患者で占められる事態を避けたい思惑があると想像される。法の適正運用と現実対応との深刻な乖離である。
VII.まとめにかえて
さて、医療観察法の地域処遇体制の問題点についてさまざま論じてきたが、そもそも鍵や塀のない茫洋とした“地域”をフィールドとした強制通院制度とか強制処遇制度といったものにリアリティがあるのか、もう一度真剣に考えてみなければならない。筆者にはそれが砂上楼閣のようにすら見える。リアリティに乏しい制度は、破綻を免れないだろう1)。それが明らかになったときに我々は何をなすべきか?国は近い将来、指定入院医療機関の不足を補うための姑息的法改正を検討せざるを得なくなると予想されるが、その機に法施行を当面凍結して抜本的に再検討することである。
再検討とは、起訴前簡易鑑定の問題を含むいわゆる検察の起訴便宜主義の是正、措置入院制度運用の標準化など、医療観察法が割って入る以前の司法と精神医療の“狭間”と言われた問題群に対して、実証的なデータに基づいて解決策を探ることを含む2)。
文献
1)岡崎伸郎:「医療観察法」施行前夜の憂鬱.精神医療,37号;87-97,2005
2)岡崎伸郎:「医療観察法」この異形の制度にどう対峙するか.岡崎伸郎,高木俊介編:動き出した『医療観察法』を検証する,pp3-7,批評社,2006
出典:社団法人日本精神神経学会の機関誌「精神神経学雑誌」第108巻第5号
関連ガイドライン
通院処遇ガイドライン.pdf(973KB)
地域社会における処遇のガイドライン.pdf(979KB)
関連文献
● 精神科医の本音トークがきける本―うつ病の拡散から司法精神医学の課題まで / 香山リカ, 岡崎伸郎. -- 批評社,2007.04. --(Psycho Critique1)